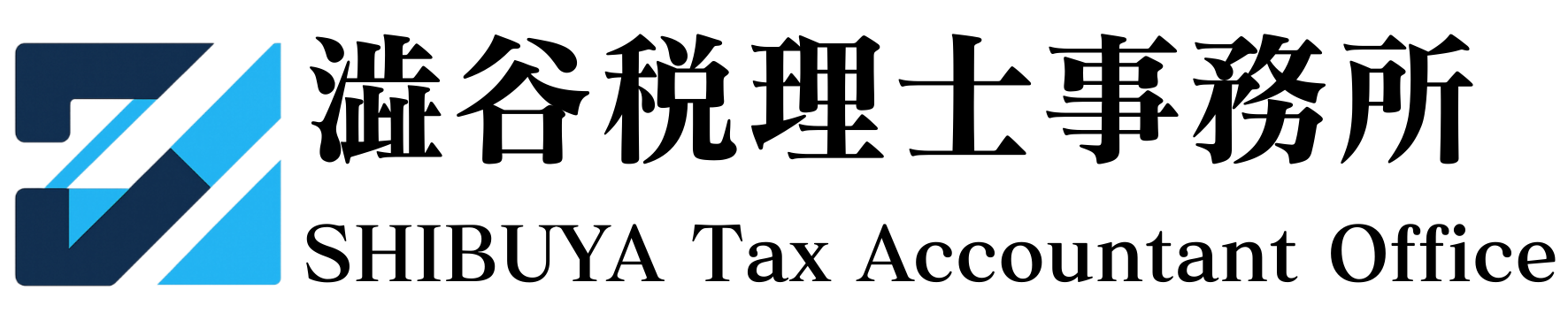- 動画制作のディレクター(発注者側)
- 個人へ動画制作を外注している事業者
- 動画制作を外注として受けている個人(受注者側)
- 年商~5,000万円規模の事業者
\ お気軽に! /
\ 契約前にサービス内容や料金を確認! /
業務委託(外注)のリスク

このように外部の第三者である個人(業務委託先)へ作業を外注しているようなケースです。動画制作業は個人で自身のスキルを活かして取り組むことが出来るため、実際に手を動かす作業自体は外部へ委託している事業者も多いのではないでしょうか。
動画制作業に限らず、フリーランスや副業がここ数年で普及してきていることに伴い、安易に外部人材を活用する事業者が増えているように思います。
雇用すると雇用する側に重責が課せられるため、外部人材を活用する方が楽、と考えている方も多いかもしれません。しかし、それほど甘くはなく、外部人材を活用するには注意しなければならない点がたくさんあります。
ここを適当にやっていると、数年後、法務・労務・税務の3分野からトリプルパンチを食らうリスクがあります。
指揮監督等はNG
ひとことで言えば、動画制作外注先に対して、まるで従業員のような扱いをすることはNGということです。
雇用と外注の良いところ取りをすることは許されません。外注先に対して業務命令を下したり、勤怠管理をしたり、福利厚生を与えたりするのは論外です。外注先のことを「うちのスタッフ」のようにHPなどで詠うなども辞めましょう。
また、外注先が主体的に動いてくれることを期待しているような求人(「その他一定の業務」など)もNGです。外注先は従業員ではないため業務内容は事前に必ず明確化しましょう。
以下の資料は具体例が充実していて読みやすい資料です。外注する側の事業者であればこちらの資料に書かれている程度の内容は必ず知っておかなければならない内容なので一読してみましょう。
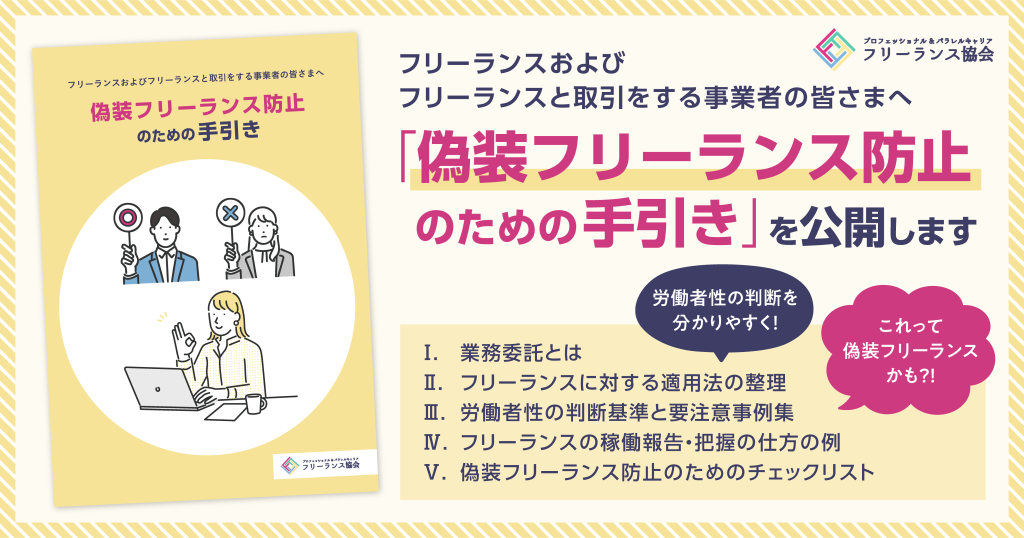
まずは弁護士等へ相談
税務の分野にも影響しますが、まずやらなければならないことは弁護士等の法務の専門家へ相談し、ご自身のビジネスモデルを説明し、どう進めていくのが適切なのかを明確にすることです。
事業者として活動してゆくならばご自身のビジネスの法的な論点なども当然に把握しておかなければなりません。もちろん精通している必要はありませんが、「これは専門家へ相談しなければならないな」と気付ける程度には知っておくべきです。
まとめ
本コラムの内容は昔からある伝統的な論点ですが、2024年11月からフリーランス保護新法が施行されたことで、このような外注先と発注者との関係におけるコンプライアンスはよりいっそう規制が厳しくなっています。
中堅規模以上の事業者であれば、事前に専門家チェックを依頼すると思いますが、特に気を付けなければならないのは創業期の事業者や年商~5,000万円規模の会社(経営者自身もまだプレイヤーとして忙しく活動しているフェーズの会社など)です。
どうしても目の前の仕事が忙しく、こういったことが手薄になりがちかもしれませんが、数年後に思わぬ地雷を踏まないように適切に進めてゆきましょう。
ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。
\ サービス範囲や料金を契約前に確認! /