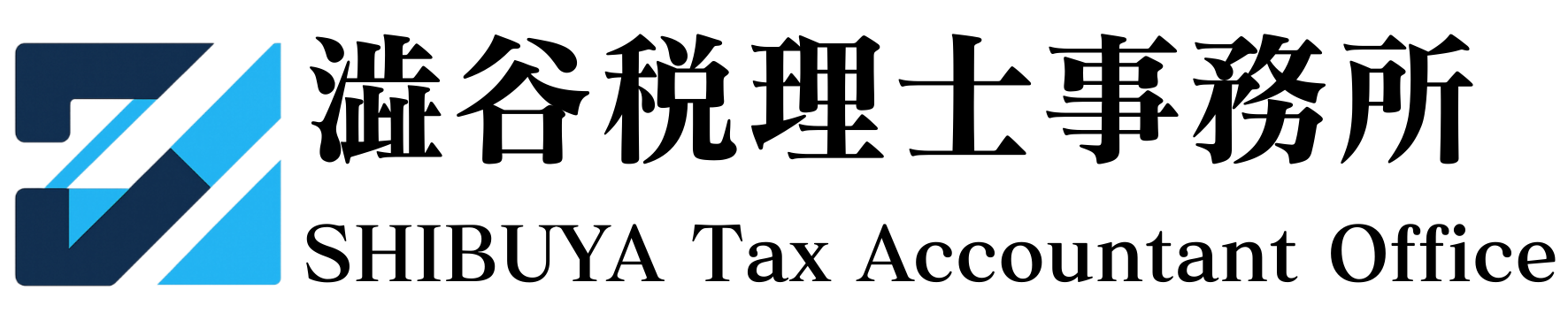- 法人成りを検討している個人事業主
- 個人事業とマイクロ法人を並走させようとしている方
\ 契約前にサービス内容や料金を確認! /
個人事業と法人化の比較
| 区分 | 項目 | 個人事業 | 法人 |
|---|---|---|---|
| 税務 | 税率 | 所得が少ないほど有利 | 所得が多いほど有利 |
| 税務申告の難度 | 相対的に低い | 相対的に高い | |
| 代表者自身に対する給与 | 所得全額 | 役員報酬※1 | |
| 親族に対する給与 | 青色事業専従者給与 | 役員報酬 | |
| 交際費等の範囲 | 相対的に狭い | 相対的に広い | |
| 生命保険 | 事業経費にならない※2 | 一定の場合には損金算入可 | |
| 社宅制度 | なし | あり | |
| 退職金 | なし | あり※3 | |
| 相続税 | 個人資産と事業資産が相続財産 | 個人資産と株式が相続財産 | |
| 損失の繰り越し | 3年間 | 10年間 | |
| 税務以外 | 社会保険 | 一定の場合以外は任意加入 | 加入必須 |
| 対外的な信用力 | 低い | 高い | |
| 求められるコンプラ | 事業主に対して | 役員⇔法人の区別 | |
| 決算日 | 12月31日 | 自由に決める | |
| 会計の難度 | 低い | 高い | |
| 事業開始の手続き | 相対的に負担が軽い | 相対的に負担が重い | |
| 廃業時の手続き | 相対的に簡易&ローコスト | 相対的に煩雑&コスト増 | |
| 事務負担※4 | 低い | 高い | |
| 諸経費※5 | ローコスト | ハイコスト |
- 1 給与所得控除あり。
- 2 生命保険料控除~12万円。
- 3 退職所得控除。
- 4 2つ(個人事業と法人事業)の会計帳簿が必要になる、法人税法上のタスクが生じる、源泉徴収事務が生じるetc.
- 5 税理士報酬が2種類(個人事業と法人事業)が生じる、社労士報酬が生じる、司法書士報酬が生じるetc.
個人事業を廃業し法人化
これは健全なケースです。事業規模が大きくなってきたときは、大口見込み顧客から「うちは法人としか契約しない」と言われたため法人化するようなケースが該当します。
個人事業主としての最後の確定申告を済ませ廃業してから、法人を設立することになります。
- 個人事業時代最後の確定申告固有の注意点(みなし譲渡、個人事業税の扱いなど)を認識していない。
- 法人へ譲渡する資産がある場合、具体的に何に気を付けるのか認識していない。
個人事業+マイクロ法人
マイクロ法人とは
主に「別でメインの収入源があり、法人を作る必然性がないが、社会保険料のコントロールなどのために作った法人」を指すときに使われることが多いです。
Youtubeなどで色々発信がされていますが、正直なところ税理士目線でみれば「おいおい…大丈夫か…?」とつっこみたくなるような内容を発信している動画も見かけます。
税理士以外の方でマイクロ法人を設立している方で個人事業と並走させることの弊害をきちんと理解している方は少ない印象です。
厳しいお話になってしまいますが、これは素人が簡単にコントロールできるものではないと認識した方が良いです。
マイクロ法人のデメリット
会計帳簿が2個へ増える
- 個人事業の会計帳簿
- 法人の会計帳簿
法人の会計帳簿は個人事業より作成の難度が上がります。
税理士報酬
- 個人事業の分の税理士報酬
- 法人の分の税理士報酬
法人化する規模でないにも関わらず法人化を進める税理士もいるかもしれませんが、これが美味しいからです。
日々の事務負担増加
- 代表者個人のプライベート経費
- 代表者の個人事業の経費
- 法人の経費
領収書などの書類についても、どれがプライベートの分で、どれが個人事業の分で、どれが法人事業の分なのか、自分で整理&管理しなければならなくなります。できない場合、いつまでたっても税理士との資料についてのやりとりが終わらず、本業に集中する時間を圧迫することとなります。
社保関係の手続き
社労士の分野になりますが法人を設立すれば社保関係の手続きが生じます。社労士報酬が当然発生します。
社労士へ依頼しないのであれば自分で自己学習して何をしなければならないのか学ぶ必要があります。
会社を閉じるときが大変
個人事業の場合、廃業するのは比較的簡単ですが、法人の場合解散手続き、清算手続きなどお金も時間も要します。
本来、会社というものは設立した時点で何年もその事業で運営していくことを前提として諸制度が作られています。ところが、マイクロ法人のような使い方をする場合、その事業に対しての本気度が低いケースが多いためそもそもこのような手続きが複雑であると認識していない方が多い印象です。
法人ならではの諸経費
個人事業時代はそれほどうるさくなかったことでも、法人設立した時点で法的に求められるコンプライアンスのレベルが一気に上がります。
何かを決めたら会社法に則って議事録作成をする必要がありますし(ご自身でできない場合は司法書士へ相談)、ちょっとした取引でも契約書を作成しなければならなかったり(ご自身でできない場合は弁護士報酬発生)、代表者個人のプライベートと法人の事業とで公私混同しないようにすることも求められます。
このような各種タスクに対処するために外部専門家への報酬が生じたり、個人事業時代にはなかった諸経費が生じます。
コンプライアンス体制
税逃れや税率コントロールのために法人設立し、収入の帰属先(個人事業or法人事業)を恣意的に(勝手に)決めることは原則として許されません。
税務調査があった際は、「なぜ取引Aから生じた収入は個人事業に帰属(所得税の税率で課税される)させていて、取引Bから生じた収入は法人の事業に帰属(法人税の税率で課税される)させているのか」といったことをご自身で説明できなければなりません。
もちろん、この整理のために税理士もサポートさせて頂きますが、最終的な経営判断は経営者ご自身にあるため、そのあたりを適切に説明できる自信がないのであれば辞めた方が良いでしょう。
- 個人事業と法人のいずれかが、事業実態が存在していない。
- 生じた取引をどちらに帰属させるのかろくに検討していない。
税理士はマイクロ法人を作っている人が多い
と、色々説教臭いことを言う税理士自身も、以下のような形態でマイクロ法人と個人事業を並走させていることが多いです。
| 事業内容 | 分類 |
|---|---|
| 税理士法上の独占業務 | 個人事業 |
| 独占業務以外※1 | 法人 |
- ※1 記帳代行や資金繰りコンサルティングなど
- 外部に依頼せずとも自分で適切にマイクロ法人の管理運営ができるため。
- 「独占業務か独占業務以外か」と基準が明確であり、個人事業も法人事業もしっかり実態が伴っているため。
個人事業とマイクロ法人を並走できそうな方
- 大口取引先から「法人でないと契約できない」と言われたなど合理的な理由がある方
- 自己学習できる方
- 専門家報酬を惜しまず支払えるほどの売上がある方
従業員を雇用するような規模の「通常の営利目的の法人」であれば自社で対応できないことは弁護士や社労士などの外部専門家へ依頼するのが常です。
マイクロ法人の場合、「専門家報酬がかかるのが嫌だ」というケースも多く、その場合は当然ご自身で法務や社保などを自己学習する必要が生じます。
厳しい話になりますが、「自己学習もしたくない」「専門家報酬がかかるのも嫌だ」という方は、「法人を経営するフェーズ」に到達していないと言えますので、やめた方が良いでしょう。
【永久保存版】会社設立・起業ガイド

まとめ
個人事業とマイクロ法人の並走は、Youtubeチャンネルや市販書籍などでいわれているほど簡単ではありませんので、それらに影響されデメリットをよく理解しないまま走り出さないよう注意しましょう。
ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。
\ サービス範囲や料金を契約前に確認! /
当サイト内の情報をご活用等される場合、以下の内容についてご同意頂いたものとみなさせて頂きますので必ずご一読下さい。
- 当サイト内の情報は正確性等を高めるよう努めておりますが、その内容に対して何らかの保証をするものではございません。
- 当サイト内の情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当サイト管理者は一切責任を負いかねます。
- 当サイト内のコラムは弊所の私見です。
- 当サイト内のコラムはその執筆時点における法令等の情報に基づき整理したものです。
最新の法改正等の内容が未反映となっている場合もあるため、必ずご自身で最新の法令等の情報をご確認下さい。 - 当サイト内の情報の無断転載等は固く禁じます。
\ 自分で会社設立! /